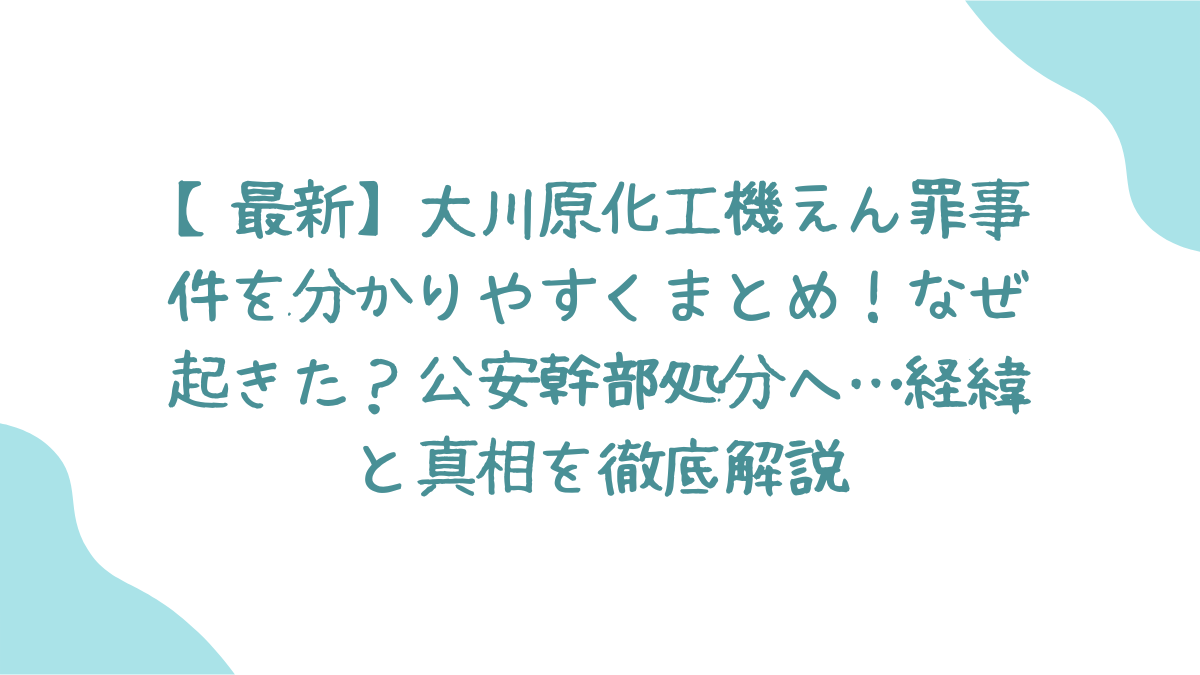ある日突然、あなたの会社が「生物兵器の製造に協力している」という身に覚えのない容疑をかけられたら、どうしますか?「まさか、そんなSFのような話が…」と思うかもしれません。しかし、これは日本で現実に起きた話です。それが「大川原化工機えん罪事件」です。
この事件、単なる警察の捜査ミスだと思っていませんか? ちょっと待ってください。その背景には、日本の司法システムが抱える、根深い「バグ」が存在するのです。今回は、この事件の経緯から、なぜこのような悲劇が起きたのか、そして最新の「公安部幹部処分」の動きまで、その本質を冷静に分析・解説していきます。
【速報】大川原化工機えん罪事件、ついに公安部幹部ら処分へ!事件の概要を分かりやすく解説
【本社訪れる】大川原化工機えん罪事件、警視庁と東京地検が社長らに直接謝罪https://t.co/lTbdufS60o
— ライブドアニュース (@livedoornews) June 20, 2025
「大川原化工機」社長らへの捜査を違法と認めた判決が確定したことを受け、警視庁と東京地検が20日午後、神奈川県横浜市にある大川原化工機の本社を訪れ、社長と元役員に直接謝罪した。 pic.twitter.com/6XdLer5KTT
2025年8月、この事件は新たな局面を迎えました。警視庁が、捜査を主導した公安部の当時の幹部らを処分する方針を固めたと報じられたのです。判決確定から約2ヶ月、重い腰を上げた形ですが、そもそもこれはどのような事件だったのでしょうか。
端的に言えば、この事件は「そもそも犯罪ではなかった」事案です。町工場が世界に誇る製品が、警察の無理な法令解釈によって「生物兵器に転用可能」と断定され、社長ら3名が逮捕・起訴されました。結果、1名は無念の死を遂げ、会社は存続の危機に立たされました。これは単なる悲劇ではなく、国家権力によって意図的に作り出された「えん罪」だったのです。
大川原化工機えん罪事件とは?なぜ「えん罪」なのか、核心を3つのポイントで解説
「えん罪」と一言で言っても、何がどう問題だったのか分かりにくいかもしれません。この事件の異常性は、主に3つのポイントに集約されます。立ち止まって考えてみましょう。これらは、決して他人事ではないのです。
ポイント1:そもそも犯罪ではなかった「輸出規制」の解釈
事件の最大の核心は、警察が法律を自分たちに都合よく「解釈」した点にあります。問題となった噴霧乾燥機(スプレードライヤー)が輸出規制の対象となる条件は、「定置した状態で滅菌又は殺菌をすることができる」ことでした。
警視庁公安部は「ヒーターで機械を空焚きすれば、内部の温度が上がって一部の菌は死ぬだろう。だから殺菌能力がある」という、かなりアクロバティックな論理を展開しました。しかし、これは国際的なルールを無視した独自解釈です。東京高裁も「合理性を欠く解釈」と断じており、そもそも犯罪の前提が崩壊していたのです。これは、ゲームのルールを運営側が自分たちに都合よく後から書き換えるようなものだと言えるでしょう。
ポイント2:現職警官も証言した「捏造」と違法な取り調べ
さらに衝撃的なのは、国賠訴訟の法廷で、捜査に関わった現職の警察官が「まあ、捏造ですね」と証言したことです。これは、組織の内部から上がった良心の悲鳴です。捜査員の個人的な功名心のために、事件が作り上げられていったというのです。
容疑者の発言を歪めて調書を作成したり、有利な弁解を記録した書面を破棄したりといった、およそ法治国家では考えられないような違法な取り調べが行われていたことも明らかになっています。これはもはや捜査ではなく、フィクションの創作活動と言っても過言ではありません。
ポイント3:無実を訴えるも11ヶ月続いた「人質司法」の実態
そして、この事件の非人道性を象徴するのが、約11ヶ月(332日間)にも及ぶ長期勾留です。日本では、無実を主張して黙秘や否認をすると、裁判所が「証拠隠滅の恐れがある」として保釈を認めない傾向があります。これを「人質司法」と呼びます。
顧問だった相嶋静夫さんは、勾留中にがんと診断されてもなお、保釈が認められませんでした。そして、釈放されないまま亡くなったのです。無実を訴えれば訴えるほど、人質として拘束され続ける。まるで、プレイヤーに不利な選択肢しかない「詰みゲー」を強制されるような、理不尽なシステムがそこにはありました。
事件の全貌を時系列で追う|逮捕から国賠訴訟の勝訴、そして警察の謝罪まで
この理不尽な物語が、どのような時間を経て「えん罪」として断罪されるに至ったのか。その道のりは決して平坦なものではありませんでした。主要な出来事を時系列で見ていきましょう。
- 2017年~:警視庁公安部が捜査を開始。経済産業省は当初、規制対象外との見解でしたが、公安部の強硬な姿勢に押し切られる形で捜査が進みます。
- 2020年3月11日:大川原正明社長、島田順司元取締役、そして顧問の相嶋静夫さんの3名が逮捕されます。ここから長い「人質司法」が始まりました。
- 2021年2月7日:逮捕から約11ヶ月後、相嶋静夫さんが勾留中に見つかった胃がんにより死去。享年72歳。最後まで無実を訴えていましたが、その名誉が生前に回復することはありませんでした。
- 2021年7月30日:検察が突如、起訴を取り消し。弁護側の証拠開示請求により、捜査の杜撰さと法令解釈の破綻が明らかになることを恐れた、異例の幕引きでした。
- 2021年9月8日~:戦いの舞台は、国と東京都を相手取った国家賠償請求訴訟へ。失われた命と時間は戻りませんが、真実を明らかにするための新たな闘いが始まりました。
- 2025年6月:東京高裁が警察・検察の捜査の違法性を断罪し、約1億6600万円の賠償を命じる判決を下します。国と都が上告を断念し、判決が確定。そして同月、警視庁と東京地検の幹部が謝罪に訪れましたが、その場で被害者の名前や社名を呼び間違えるという、信じがたい失態を犯しました。
この一連の流れは、権力機関がいかにして暴走し、その間違いを認めるまでにどれほどの時間と犠牲を要するかを物語っています。
なぜえん罪事件は起きたのか?警察の暴走と司法の闇を3つの側面から深掘り
では、なぜこれほどまでに常軌を逸した事件が起きてしまったのでしょうか。背景には、警察、検察、そして司法制度それぞれが抱える、構造的な問題が存在します。この3つの側面から、事件の深層を分析してみましょう。
原因① 功を焦った公安部の暴走と「事件の捏造」疑惑
一つ目の原因は、手柄を立てることに焦った警視庁公安部の暴走です。報道によれば、当時、捜査を担当した部署は「目立った成果を上げていない」というプレッシャーの中にあったとされています。「経済安全保障」が叫ばれる時代の空気の中、不正輸出という「分かりやすい事件」を作り上げることで、組織内での評価を得ようとしたのではないか。そう疑われても仕方がありません。
「この法律はザルだ」「警察が勝手に位置付けできる」といった捜査幹部の発言は、法を守るべき者の発言とは到底思えません。成果を求めるあまり、ルールをねじ曲げてでもゴールを奪いに行く。しかし、それはもはや正当な職務執行ではありませんでした。
原因② 警察の言いなりだった?機能しなかった検察のチェック体制
二つ目は、警察の捜査をチェックするべき検察が、その役割を全く果たさなかったことです。本来、検察官は警察から送られてきた事件を客観的に検討し、不当な起訴を防ぐ「最後の砦」のはずです。
しかし、本件を担当した検事は、警察の無理な法令解釈を鵜呑みにし、立件に不利な証拠がありながら起訴に踏み切りました。国賠訴訟の法廷で「謝罪の気持ちはない」と述べたその姿勢は、チェック機能が麻痺していたことの証左です。警察というフォワードの暴走を、本来止めるべき検察というディフェンダーが、見て見ぬふりをした。この無責任な連携プレーが、悲劇を拡大させました。
原因③ 無実でも自白を強いる「人質司法」という日本の大問題
三つ目にして最大の問題が、前述した「人質司法」という構造的な欠陥です。無実を証明しようとすればするほど、身体拘束が長引く。この理不尽なプレッシャーは、無実の人にすら「嘘でも罪を認めた方が早く出られる」と思わせてしまう危険性をはらんでいます。
相嶋さんががんに罹患してもなお保釈されなかった現実は、この制度が人の命よりも「証拠隠滅の恐れ」という抽象的なリスクを優先する、非人道的なものであることを示しています。「推定無罪」という近代司法の大原則が、日本ではいとも簡単に覆されてしまう。この事件は、その冷徹な事実を私たちに突きつけました。
事件のキーパーソン|被害者と捜査を主導した警察官・検察官はどんな人物?
この事件は、抽象的な制度の問題であると同時に、生身の人間たちの物語でもあります。被害に遭った技術者たちと、捜査を主導した側の人物像を見てみましょう。
被害者:大川原正明社長と亡くなった相嶋静夫さん、家族の苦悩
被害を受けたのは、噴霧乾燥機の国内シェア7割を誇る、世界的な技術力を持つ中小企業でした。社長の大川原正明氏は、無実を信じ、屈することなく闘い抜きました。そして、技術部門のトップとして会社を支え、後進の育成に尽力していた相嶋静夫さん。彼の技術への情熱と誇りは、冷たい拘置所の壁の中で踏みにじられ、その命まで奪われました。
捜査側:捜査を指揮した警視庁公安部の警察官と担当検事
一方、捜査を指揮した当時の係長・宮園勇人元警視は、事件後に昇進し、定年退職しています。また、違法な取り調べで告発された安積伸介警部も昇進しています。違法な捜査を主導した者が罰せられることなく、内部告発した者が冷遇される。この構図自体が、組織の病理を物語っています。
今後どうなる?公安部の幹部処分と求められる再発防止策
判決が確定し、世論の批判が高まる中、ようやく警察・検察は重い腰を上げました。しかし、発表された対応は十分と言えるのでしょうか。
処分対象は20人規模か?退職者も含む処分の内容
【警察当局は退職者を含む歴代の幹部らを処分 または処分相当とする方針】
「大川原化工機」のえん罪事件で警視庁が近く検証結果を公表する方向で調整していることが分かりました。NHKプラスで見逃し配信https://t.co/RGeQSaKf4K最新情報はこちらhttps://t.co/HZOF3pXcGd pic.twitter.com/B9pEmZxm49— NHK おはよう日本 公式 (@nhk_ohayou) August 3, 2025
警察当局は、当時の公安部長や参事官を含む、退職者も含めた複数人の処分を検討していると報じられています。しかし、最も重要なのは処分の重さや人数ではありません。なぜ彼らの暴走を止められなかったのか、その組織的な原因を徹底的に究明することが不可欠です。トカゲの尻尾切りで終わらせては、何の意味もありません。
「捜査指導室」の新設…本当に再発防止策は機能するのか?
警視庁は再発防止策として、第三者の目で証拠を吟味する「捜査指導室」の新設などを発表しました。聞こえはいいですが、問題は「誰が」「どうやって」チェックするのかです。結局、同じ組織内の人間がチェックするのでは、馴れ合いや忖度が生まれる余地が残ります。相嶋さんの遺族が求めているように、外部の第三者を入れた徹底的な検証なくして、真の再発防止はあり得ないでしょう。
残された課題:相嶋さんの死と司法が向き合うべき責任
そして何より、この事件で失われた相嶋さんの命は二度と戻ってきません。遺族は警察の謝罪を拒否し、真相究明を求め続けています。制度改革はもちろん重要ですが、国家権力の過ちによって一人の人間の尊厳と命が奪われたという事実に対し、司法全体がどう向き合っていくのか。その重い責任が問われ続けています。
まとめ:大川原化工機えん罪事件が私たちに問いかけること
さて、ここまで大川原化工機えん罪事件を深掘りしてきましたが、いかがでしたでしょうか。この事件は、決して「公安警察」という特殊な部署だけの問題ではありません。
「人質司法」の温床となっている長期勾留、機能しない検察のチェック体制、そして一度走り出したら止まれない捜査機関の組織論理。これらの問題は、日本の刑事司法全体に横たわる根深い課題です。この事件は、その課題が最も不幸な形で噴出したケースと言えるでしょう。
経済安全保障が重要視される時代だからこそ、捜査機関と民間企業との信頼関係は不可欠です。しかし、この事件は「いつ自分たちが標的にされるか分からない」という深刻な不信感を産業界に植え付けました。相嶋静夫さんの無念の死を無駄にしないためにも、この事件を単なる一つの不祥事として終わらせず、私たち市民一人ひとりが、日本の司法制度全体の改革を求める声を上げ続けることが重要ではないでしょうか。