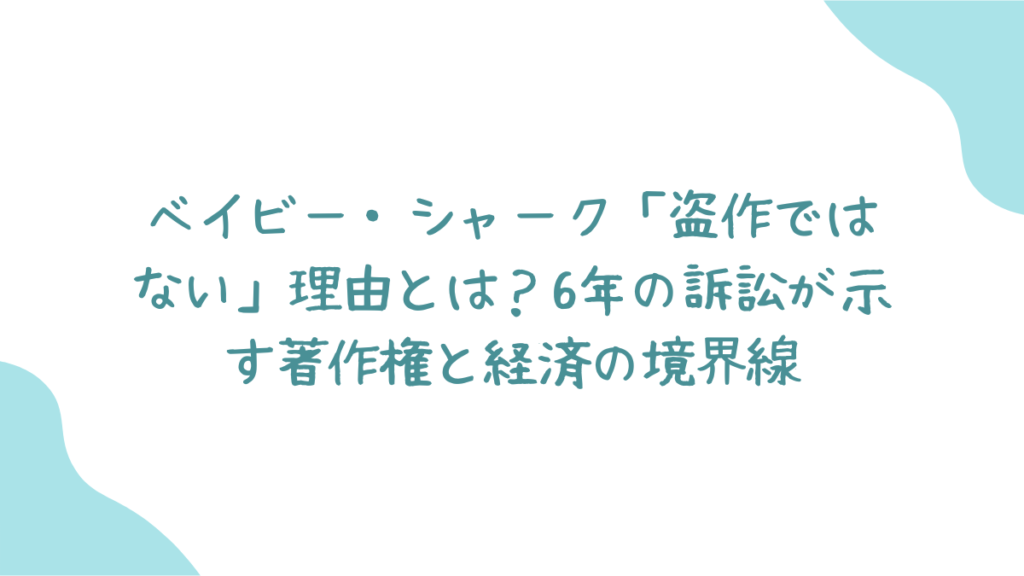世界で最も再生されたYouTube動画、「ベイビー・シャーク」。その裏で6年にも及ぶ「盗作」を巡る法廷闘争が繰り広げられていたことをご存知でしょうか。2025年8月、韓国最高裁は制作会社ピンクフォンの勝訴を確定させ、この論争に終止符を打ちました。
しかし、一度立ち止まって考えてみましょう。なぜこの童謡は、これほどまでの世界的コンテンツに成長し、そして深刻な著作権紛争の火種となったのでしょうか。この判決は、単なる一企業の勝利を意味するだけではありません。デジタル時代における文化の所有権と経済的価値の本質を、私たちに鋭く問いかけているのです。
ベイビー・シャークは「盗作」なのか? 6年間の法廷闘争が問いかけた本質
「ベイビー・シャーク」の著作権訴訟、韓国最高裁でピンクフォンが勝利 https://t.co/4W3Rc92RC3
— cnn_co_jp (@cnn_co_jp) August 14, 2025
まず事実関係を整理しましょう。2019年、米国の作曲家ジョニー・オンリー氏は、ピンクフォン社の「サメのかぞく(ベイビー・シャーク)」が、自身が2011年に発表したバージョンを盗用したものだとして訴訟を提起しました。しかし、最終的に韓国最高裁は「盗作にはあたらない」と結論づけました。その最大の根拠は、両者の楽曲の元となったものが、作者不詳のパブリックドメイン(公有財産)である口承民謡だった点にあります。
この状況は、言わば先祖代々伝わる秘伝のタレ(パブリックドメイン)に、少しだけスパイス(軽微なアレンジ)を加えた料理人が「これは完全に自分のオリジナル料理だ」と主張するようなものです。裁判所は、オンリー氏のアレンジが「社会通念上新しい著作物になり得る程度の創作性」を持たないと判断しました。これは、デジタル時代のコンテンツ制作における「創造性」の基準を考える上で、極めて重要な判断と言えるでしょう。
口承文化とデジタル経済の衝突:著作権の境界線はどこにあるのか
この訴訟の核心は、形のない「口承文化」が、いかにして具体的な「著作権」や「経済的価値」に変換されるのか、という問題です。その境界線は、驚くほど曖昧なものの上に成り立っています。
起源はドイツの民謡? パブリックドメインという「共有財産」
「ベイビー・シャーク」のルーツを辿ると、ドイツの童謡に行き着き、それが米国に伝わってサマーキャンプの定番ソングになったとされています。つまり、この曲は特定の誰かのものではなく、文化という大きな鍋で煮込まれてきた「共有財産」なのです。ピンクフォン社は、この共有財産を現代的なポップサウンドとキャッチーなダンス映像という器に盛り付け、YouTubeという世界最大の食卓に提供することで、莫大な利益を生み出しました。
これは、伝統文化がデジタルプラットフォームと結びつくことで、想像を絶する経済圏を生み出す可能性を示しています。一方で、その果実を誰が手にするのか、という新たな分配の問題も浮き彫りにしました。
二次的著作物が認められる「創作性」の壁
では、どこからが「模倣」で、どこからが「創造」なのでしょうか。今回の判決は、二次的著作物として法的に保護されるためには、原曲に対して「新たな創作性が付加」されていなければならない、という厳しい基準を示しました。
この「創作性の壁」は、今後のクリエイターに重大な問いを投げかけます。
- 単なる楽器の変更やテンポの調整は「創造」と言えるのか?
- メロディーや歌詞にどれほどの独自性を加えれば、それは「新しい作品」として認められるのか?
- AIが既存の作品を学習し、無数のバリエーションを生成する時代に、人間の「創作性」はどこに見出されるのか?
この問題は、スマートフォンの料金プラン選びとよく似ています。基本プラン(パブリックドメイン)は誰でも利用できますが、本当に価値があるのは、他社にはない魅力的なオプション(独自の創作性)をどれだけ付加できるかにかかっているのです。
YouTubeが生んだモンスター:160億回再生の経済的インパクトと文化的意味
この一件を単なる著作権訴訟として片付けることはできません。背景には、YouTubeというプラットフォームが生み出した、あまりにも巨大な経済的・文化的影響が存在します。
3000万ウォン vs 数十億ドル:訴訟額が示す「ブランド価値」の非対称性
原告が請求した損害賠償額は約3,000万ウォン(約216万円)。対して、「ベイビー・シャーク」関連ビジネスの市場規模は数十億ドル(数千億円)規模に達します。この圧倒的な金額の差は、デジタルコンテンツの価値が、もはや楽曲そのものではなく、そこから派生するキャラクターやブランドという無形資産に宿っていることを示しています。
皮肉なことに、6年間の訴訟はピンクフォン社の知名度をさらに高め、結果としてブランド価値を補強する役割さえ果たしました。これは、巨大プラットフォーム経済の中で、個人のクリエイターが巨大資本といかに非対称な戦いを強いられるかという、現代社会の構造的な問題点を象徴していると言えるかもしれません。
K-POPに続く文化輸出コンテンツとしての「ベイビー・シャーク」
韓国政府や釜山市が「ベイビー・シャーク」を公式に活用し、万博誘致のシンボルとしている事実は見逃せません。これは、この童謡が単なるヒット曲ではなく、K-POPに続く国家的な文化輸出戦略の一翼を担っていることを意味します。
かつて文化は、地理的な制約の中でゆっくりと伝播していくものでした。しかし現代では、YouTubeやTikTokのようなプラットフォームを介して、一つのコンテンツが瞬時に国境を越え、経済的、さらには政治的な影響力を持つ「ソフトパワー」へと変貌するのです。この速度と規模は、我々の文化に対する認識そのものを変えつつあります。
よくある質問と回答
Q. 結局、「ベイビー・シャーク」の曲は誰でも自由に使っていいのですか?
A. 元になった口承民謡はパブリックドメインなので、誰でも自由にアレンジして利用できます。ただし、ピンクフォン社が制作した特定の音源や映像、キャラクターには著作権と商標権が存在するため、それらを無断で使用することはできません。重要なのは「元のアイデア」と「具体的な表現」を区別することです。
Q. なぜ裁判は6年以上も長引いたのでしょうか?
A. この訴訟が、デジタル時代の著作権に関する極めて新しい論点を含んでいたためです。口承民謡をベースにした二次的著作物の「創作性」の程度をどう判断するか、という前例の少ない問題だったため、地裁から最高裁まで慎重な審理が必要とされました。また、関わるビジネスの規模が巨大だったことも、紛争が長期化した一因です。
Q. この判決は、今後の音楽やコンテンツ業界にどんな影響を与えますか?
A. パブリックドメインの楽曲をアレンジする際の「創作性」のハードルが明確になったことで、クリエイターはより高い独創性を求められるようになります。安易なアレンジは法的リスクを伴う可能性がある一方、企業は知的財産のクリアランス(権利処理)をより重視するようになるでしょう。これは業界全体の質の向上に繋がる可能性があります。
まとめと今後の展望
「ベイビー・シャーク」を巡る6年間の法廷闘争は、パブリックドメインという人類の共有財産をベースにしたデジタルコンテンツが、どこから法的に保護されるべき「私有財産」になるのか、その境界線を示しました。答えは、単なるアレンジを超えた「本質的な創作性」の有無にあります。
この一件は、私たちに多くの問いを投げかけます。クリエイターには「真の創造とは何か」を。企業には「知的財産の戦略的価値」を。そして社会全体には「文化は誰のものか」という根源的な問いを。AIが自動でコンテンツを生成する未来が目前に迫る今、この問いの重みは増すばかりです。私たちは、文化と経済が複雑に絡み合うこの新しい海を、どう航海していくべきかを真剣に考えなければならない時期に来ているのです。
参考文献
- CNN:’Baby Shark’ creator wins 6-year copyright battle in South Korea’s Supreme Court (出典)
- 聯合ニュース:[速報]「サメのかぞく」の著作権訴訟 ピンクフォンが最終勝訴=韓国最高裁 (出典)
- BBC News:Baby Shark: How a YouTuber’s version of the song became a global hit (出典)
- 朝鮮日報:「サメのかぞく」著作権訴訟、ピンクフォン・カンパニーが米作曲家に最終勝訴 (出典)